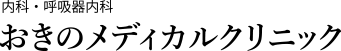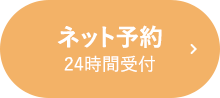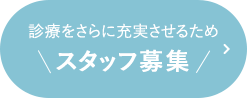高尿酸血症とは
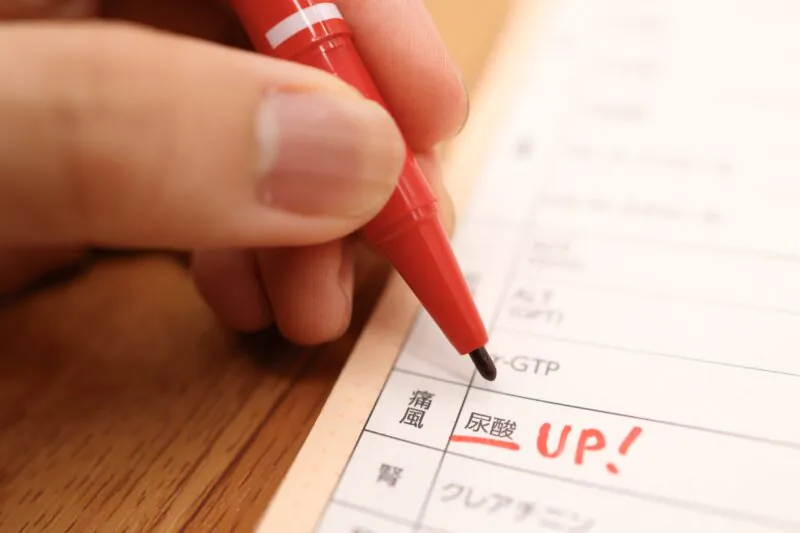
尿酸は体内で生成される老廃物の一種であり、その名の通り、主に尿を通じて体外に排出されます。健康診断などで血液検査を受けると、通常、尿酸値が測定されます。
尿酸値とは、血液中の尿酸濃度のことです。尿酸値が基準値の7.0mg/dlを超えると、高尿酸血症と診断されます。
尿酸値が高くても自覚症状はありませんが、高尿酸血症が長期間続くと、尿酸が結晶を形成し、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。
高尿酸血症は男性に多い病気
高尿酸血症は特に男性に多い病気です。女性の発症が比較的少ないのは、女性ホルモンの働きによるものです。女性ホルモンには腎臓からの尿酸の排泄を促す作用があり、尿酸が適切にコントロールされると考えられています。したがって、閉経により女性ホルモンが低下すると、女性でも尿酸値が上昇しやすくなり、高尿酸血症のリスクが高まります。
高尿酸血症の代表的な合併症

高尿酸血症(尿酸値が高い状態)が長期間続くと、体のさまざまな部位に尿酸の結晶が沈着してしまいます。その結果、さまざまな臓器に障害を引き起こす可能性があります。
これによる合併症としては、以下のものが挙げられます。
- 痛風
- 慢性腎臓病(腎不全)
- 尿路結石(尿酸結石)
尿酸値が高くても自覚症状はないため、放置すると激しい痛みを伴う痛風発作や尿路結石を引き起こす可能性があります。また、命に関わる重大な病気のリスクも高まります。
少しでも気になる方は、お早めに当院までご相談ください。
痛風
痛風は、血中の尿酸レベルが異常に高くなる高尿酸血症によって引き起こされる関節炎の一種です。足の関節に尿酸結晶が沈着し炎症を起こすと、激しい痛みで知られる痛風発作が起こります。赤み、腫れ、熱感も痛風の特徴的な症状です。
高尿酸血症が長く続くと、尿酸結晶は皮膚の下や腱などにもたまり、痛風結節を形成します。これらの結節は主に手の指や足のつま先、肘、耳たぶなどに現れますが、関節以外の場所にもできることがあります。
痛風結節自体はあまり痛みを引き起こしませんが、大きくなりすぎると動きを妨げたり、感染のリスクを高めたりすることがあります。また、見た目の問題にもつながることがあります。
痛風や痛風結節の治療には、ライフスタイルの変更、食事療法、薬物療法が含まれます。これらの治療は尿酸レベルを下げ、痛風発作の頻度や重症度を減らすことを目的としています。
腎障害
高尿酸血症が長期間続くと、腎臓の機能障害が起こる可能性があります。尿酸は通常、血液を通じて腎臓に運ばれ、尿として体外に排出される人体の代謝過程の副産物です。しかし、血中の尿酸レベルが異常に高くなると、腎臓がそれを完全に処理できなくなり、尿酸結晶が腎臓内にたまることがあります。これが続くと腎機能が低下し、慢性腎臓病の原因となることがあります。進行すると腎不全に至ることもあります。
痛風による腎障害のリスクを減らすためには、血中の尿酸レベルを管理し、健康的な食生活を心がけ、適切な体重を維持することが重要です。また、痛風を適切に管理し、医師の指示に従って薬物治療を受けることも腎障害の進行を防ぐために必要です。
尿路結石(尿酸結石)
尿酸結石は尿路結石の一種で、特に尿が酸性の場合にできやすいです。尿酸値が異常に高くなると、尿中の尿酸が過飽和状態になり、結晶化して尿酸結石が形成されます。結石が小さい場合は自然に尿と一緒に排出されることがありますが、大きくなると尿路を塞ぐ可能性があり、激しい痛みが生じることがあります。
尿酸値を適切なレベルに保つためには、健康的な食生活、適度な運動、十分な水分摂取、体重管理が重要です。他の疾患と同様にこれらを意識して取り組むことが大切です。
生活習慣病との合併に注意
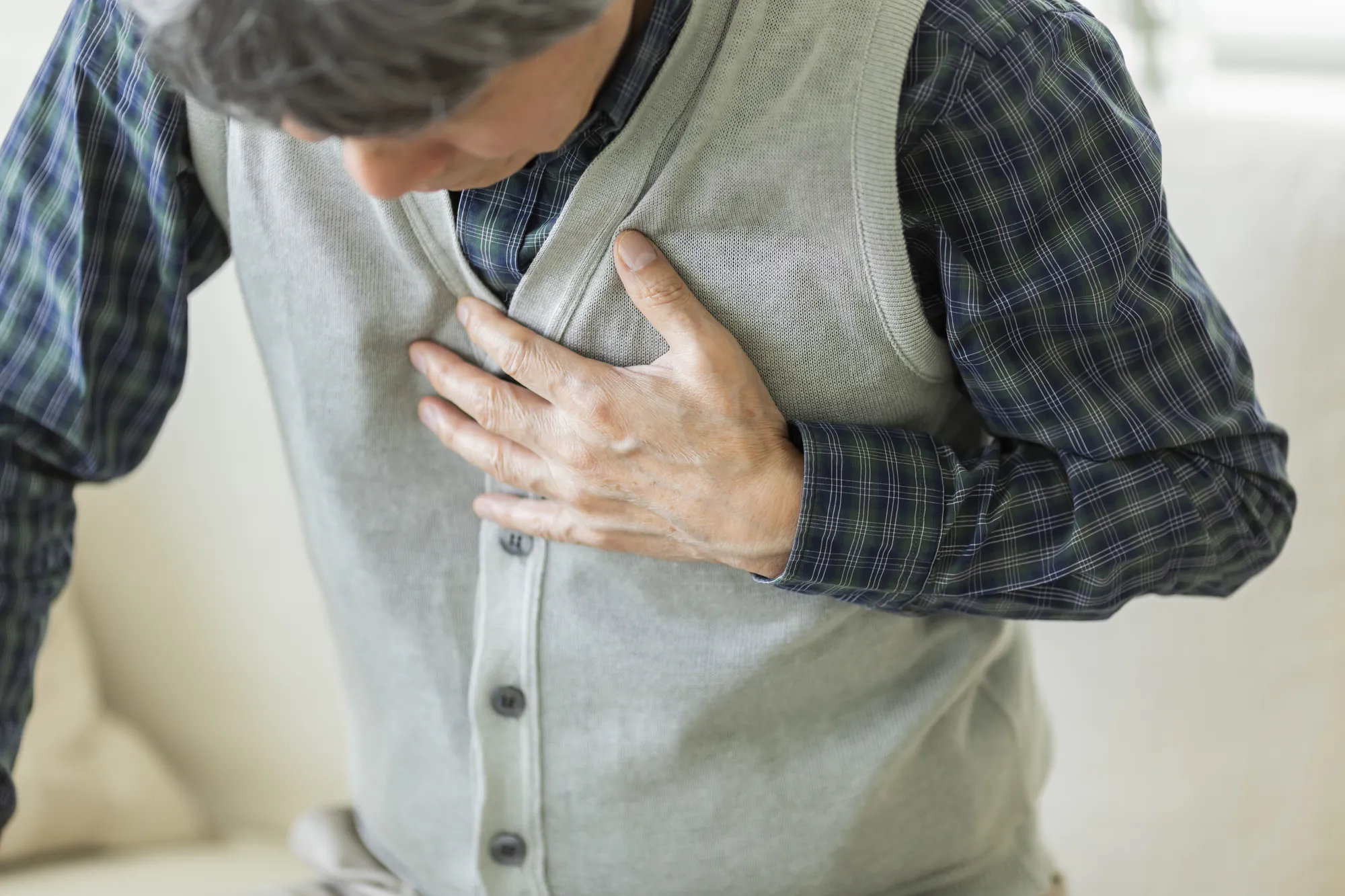
高尿酸血症は、尿酸結晶が直接の原因とは言えない生活習慣病と一緒に現れやすいことがわかっています。
例えば、高血圧や脂質異常症、糖尿病、内臓脂肪型肥満などの生活習慣病と高尿酸血症が結びつくと、動脈硬化が進行しやすくなります。その結果、心臓や脳の血管に障害が起こるリスクが高まります(例:心筋梗塞や脳卒中)。尿酸値が高くない人でもこれらの病気にかかることがありますが、尿酸値が高いほどリスクが高まる傾向があります。
このように、高尿酸血症では、他の重大な病気が合併しやすく、注意が必要です。
高尿酸血症の原因
食品に含まれるプリン体は、尿酸の元になることで知られています。しかし、体内で作られる尿酸の約20%がプリン体からであり、残りの80%は体内エネルギーや遺伝子由来の老廃物です。
尿酸が過剰に生成されたり、効果的に尿中に排出されなかったりすると、血中の尿酸が増えて高尿酸血症を引き起こすことがあります。尿の量が少なかったり、尿が酸性になると、尿酸が効率よく排泄されなくなります。1日に2リットル以上の水分を摂ることが推奨されていますが、甘い飲み物は肥満につながる可能性があるので過剰に摂取しないように注意しましょう。
高尿酸血症と診断されたら
まずは生活習慣の改善を

高尿酸血症といわれたら、薬物治療の前に、生活習慣を見直すことが大切です。
運動療法
高血圧や糖尿病などの生活習慣病を予防するためには、適度な運動がおすすめです。
過度な筋力トレーニングや激しい運動などの無酸素運動を行うと、逆にエネルギーの余剰分である尿酸が増え、尿酸値が上昇しやすくなります。
既に高尿酸血症の場合は、ウォーキングなどの軽い有酸素運動を毎日継続することが効果的です。有酸素運動は体重を減らし、肥満を予防し、健康を促進するのに役立ちます。
食事療法
食事療法も効果的です。プリン体を多く含む食品を控え、尿をアルカリ化する食品を増やし、尿を酸性化する食品を減らして、毎日の食事を工夫しましょう。
プリン体が多い食品には、鶏や豚、牛のレバー、干物(イワシやアジ)、カツオ、牛ヒレ肉などがあります。これらの食品を過剰に摂取せず、少量で楽しむことが高尿酸血症の予防に役立ちます。一方で、ひじきやわかめ、大豆、しいたけ、野菜、イモ類は尿をアルカリ化するため、積極的に摂取しましょう。卵や肉類、魚介類は尿を酸性化させ、尿酸の排泄を低下させます。
また、ビールにはプリン体が多いことが知られていますが、「焼酎は大丈夫」というわけではありません。すべてのアルコール類には尿酸を増やす作用があるため、過度な飲酒は避けましょう。一日あたりの適切な飲酒量は、ビールなら500ml、25度の焼酎なら90ml、日本酒やワインなら180ml、40度のウイスキーなら60mlが目安です。
高尿酸血症の治療
 痛風と高尿酸血症の治療は別々に考える必要があります。痛風になってしまった場合は、まずは炎症を抑える治療を行うことが重要です。その後、原因となっている高尿酸血症の治療についても検討していきますが、これらは別々の段階で進めることが一般的です。
痛風と高尿酸血症の治療は別々に考える必要があります。痛風になってしまった場合は、まずは炎症を抑える治療を行うことが重要です。その後、原因となっている高尿酸血症の治療についても検討していきますが、これらは別々の段階で進めることが一般的です。
痛風による関節炎の治療
痛風関節炎には、まず鎮痛と抗炎症のために非ステロイド抗炎症薬が使われます。特に痛風発作のピーク時には、比較的多量の非ステロイド抗炎症薬を使うことが推奨されています。関節炎が改善すれば、薬の投与も中止します。
ただし、腎機能障害や胃潰瘍のある人には、多量の非ステロイド抗炎症薬を使うと問題を引き起こすことがあります。そのような場合や非ステロイド抗炎症薬が効かない場合には、ステロイド剤を使うこともあります。また、痛風発作の前兆期にはコルヒチンを服用することも有効です。
高尿酸血症の治療目標
高尿酸血症に対しては、生活習慣の改善だけではコントロールできない場合に、尿酸降下薬を使った薬物治療が行われます。この治療は、痛風関節炎の再発や慢性化を予防し、尿酸血症による臓器障害(尿路結石や腎機能障害)を防ぐことを目的としています。尿酸降下薬は長期間にわたって服用する必要があるため、治療効果や副作用を確認するためには、定期的に血液検査や尿検査を受ける必要があります。
日本痛風・核酸代謝学会のガイドラインでは、高尿酸血症の治療方針が示されています。
痛風発作の既往がある場合は、血清尿酸値を低く保つ必要があり、原則として薬物治療が必要です。具体的には、血清尿酸値を6.0mg/dl以下に下げることを目標とします。
痛風発作の既往がない場合は、以下の基準に従って治療が行われます。
- 血清尿酸値が8.0mg/dl未満の場合:生活指導のみで経過を観察します。
- 血清尿酸値が8.0mg/dl以上の場合:合併する病態(肥満、高血圧、高脂血症、虚血性疾患、耐糖能異常など)があれば薬物治療を検討します。
- 血清尿酸値が9.0mg/dl以上の場合:薬物治療を検討します。
尿酸降下薬の投与方法
尿酸降下薬には、「尿酸の排泄を促進する薬」と「尿酸の生成を抑える薬」があります。高尿酸血症の原因が尿酸排泄が低下しているタイプなのか、尿酸生成が過剰になっているタイプなのかを判断することが望ましいですが、混合型もあるため、はっきりしないこともあります。
尿酸排泄が低下している場合は、尿酸排泄を促進する薬を使い、尿酸生成が過剰な場合は、尿酸生成を抑える薬を使うことが理にかなっていますので、できる限り区別するようにします。ただし、尿路結石や腎障害がある場合には、尿酸生成を抑える薬が第一選択となります。
尿酸生成を抑える薬には、アロプリノール(ザイロリック、アロプリノーム)、フェブキソスタット(フェブリク)、トピロキソスタット(トピロリック)があります。
尿酸排泄を促進する薬には、ベンズブロマロン(ユリノーム)、プロベネシド(ベネシッド)、ドチヌラド(ユリス)があります。尿が酸性(尿pH6.0未満)の場合、尿中で尿酸結晶化が促進され、尿路結石や腎機能障害のリスクが高くなります。尿酸排泄促進薬を使う場合は、尿をアルカリ化するクエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠(ウラリット配合錠)と併用します。
また、痛風発作中に尿酸降下薬を始めると、関節炎が悪化したり、慢性化することが知られています。急激に血清尿酸値を下げると、関節内の尿酸塩結晶が関節内に剥脱しやすくなるためです。
そのため、痛風発作中には尿酸降下薬の開始や増量は避けます。尿酸降下薬を始めるタイミングは、痛風発作が治まった2週間後くらいが適しています。最初は少量から始め、血清尿酸値を見ながらゆっくりと増やしていきます。