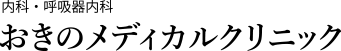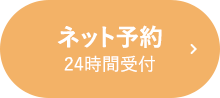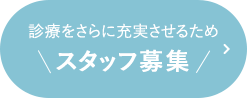高血圧症とは
 高血圧症とは、血圧が通常よりも高くなってしまう状態のことです。
高血圧症とは、血圧が通常よりも高くなってしまう状態のことです。
症状はまったくないのに、健康診断などで血圧を測定して『血圧が高いですね』と言われたことがある人は多いかもしれませんね。でも、それですぐ高血圧という病名が確定するわけではありません。血圧は一日のうちでも変動があり、高くなったり低くなったりしています。
健康診断や病院で血圧を測定するとき、たまたま高くなってしまうこともあるので、1回だけで高血圧と診断されるわけではありません。
血圧は1日のうちでも変動があります。また、緊張や不安で血圧が上昇することを「白衣高血圧」と呼びます。白衣高血圧は将来的に高血圧になる可能性があるため、注意が必要です。
本稿の内容を動画でも説明します。
高血圧とはどのような状態?
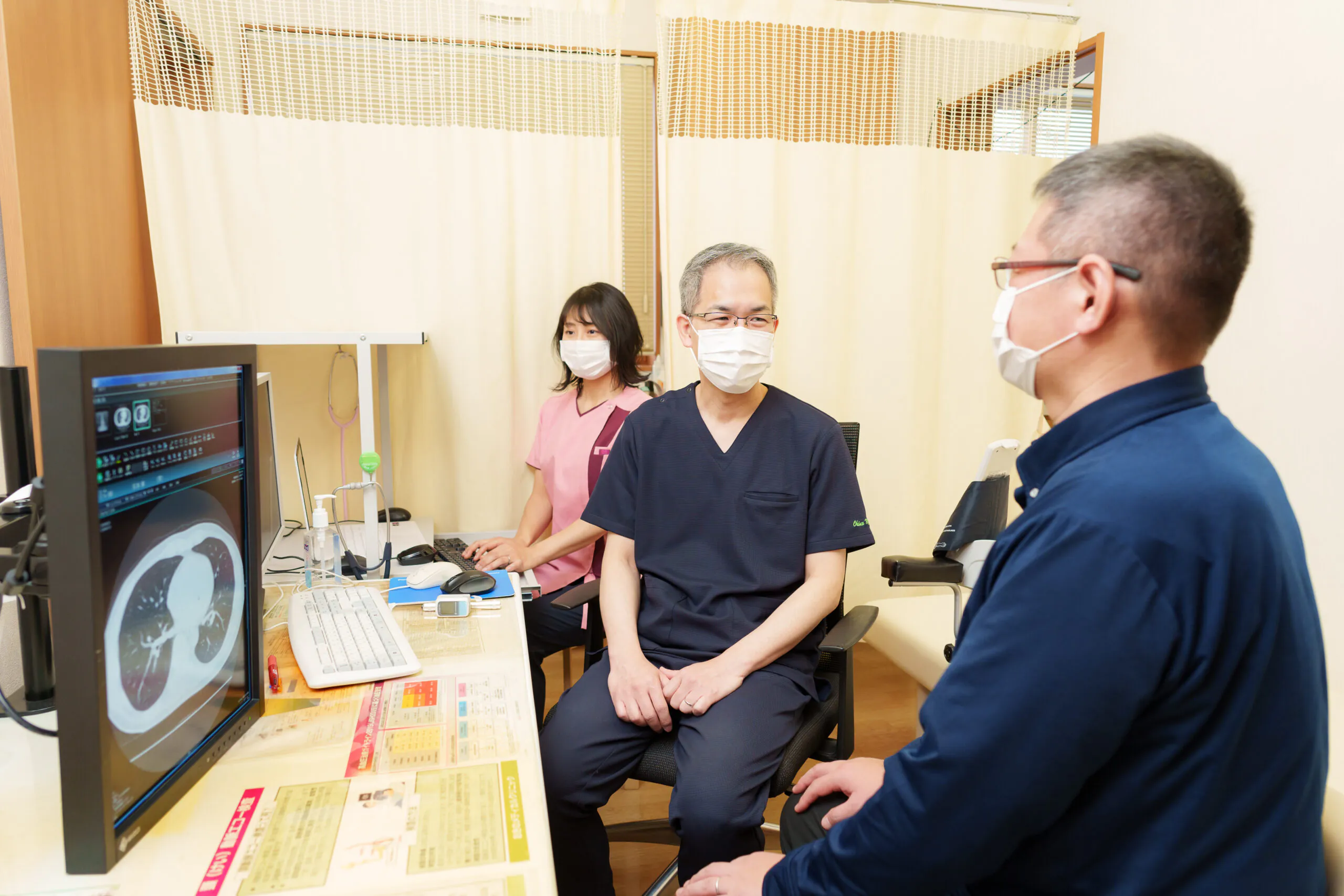 まずは家庭で血圧を1週間測定してもらいます。ベストなのは、起床時と就寝前の2回測定することですが、困難な場合は起床時のみでもかまいません。そして、起床時と就寝前の血圧の平均値をとります。
まずは家庭で血圧を1週間測定してもらいます。ベストなのは、起床時と就寝前の2回測定することですが、困難な場合は起床時のみでもかまいません。そして、起床時と就寝前の血圧の平均値をとります。
「収縮期血圧(上の血圧)が140以上、かつ/または 拡張期血圧(下の血圧)が90以上」であれば、高血圧と診断されます。
2019年高血圧治療ガイドラインによると、「正常血圧は収縮期血圧が120未満、かつ拡張期血圧が80未満」となっています。
ただし、高血圧と正常血圧の間には、血圧がどちらとも言えない状態があります。それは、正常高値血圧(120-129かつ<80) 高値血圧(130-139かつ/または80-89)です。
このような余分な血圧が設定された理由については、専門的な説明が必要となりますが、これらの状態も血圧が高めであるため、注意が必要です。
血圧が120/80を超える方は要注意
血圧が120/80を超えると、心血管系の合併症のリスクが少しずつ増加していきます。例えば、血圧が120の人よりも130の人の方が、血圧が130の人よりも140の人の方が、血圧が140の人よりも150の人の方が、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高くなります。
一般的に、高血圧は血圧が140以上かつ/または90以上の場合とされていますが、人によって適正な血圧は異なります。糖尿病や慢性腎臓病など高リスクの病気を抱えている方は、血圧が140未満でも薬物治療が必要となることがあります。
高血圧の定義は難しいですが、その人にとって健康に悪影響を与える、または将来的に悪影響を及ぼす可能性がある血圧を、その人にとっては高血圧と考えることができます。自覚症状がなくても、高血圧は全身の血管を傷め、臓器に障害を引き起こす可能性があります。
血圧が高いと言われた場合、まずはご自宅で1週間に渡って血圧を測定してみましょう。血圧測定は自分で簡単にできる検査です。平均値を計算して、収縮期血圧が140以上、または拡張期血圧が90以上の場合は、必ずクリニックを受診しましょう。
140/90以下でも、生活習慣の改善が必要で、場合によっては薬の治療が必要になることがあります。受診をおすすめします。
高血圧症を放っておくと
 高血圧による頭痛やふらつきなどの症状がある場合は、自分で高血圧を発見することができるかもしれませんが、大半の人は症状がなく、自分の血圧が高いことに気づきにくいです。健康診断を受けないと、自分の血圧が高いことに気づくことは難しいでしょう。
高血圧による頭痛やふらつきなどの症状がある場合は、自分で高血圧を発見することができるかもしれませんが、大半の人は症状がなく、自分の血圧が高いことに気づきにくいです。健康診断を受けないと、自分の血圧が高いことに気づくことは難しいでしょう。
高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれ、放置すると命に関わる病気です。自分の血圧が高いことを知らなかったり、何年も放置したりすると、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な病気になる可能性があります。
命を守るためにも、定期的な健康診断やご自宅で血圧を測定することが大切です。
高血圧を放置すると、なぜ危険?
 高血圧を放置すると、なぜ危険なのかを詳しく解説します。
高血圧を放置すると、なぜ危険なのかを詳しく解説します。
私たちの体は、心臓と全身の臓器をつなぐ血管で構成されています。血管には動脈と静脈がありますが、血圧の影響を受けるのは主に動脈です。動脈は、チューブやホースのように単純な管ではありません。動脈の壁には、平滑筋という筋肉が張り巡らされています。この平滑筋のおかげで、動脈には弾力性があるのです。
心臓が収縮すると、動脈内の圧が高くなります(これを収縮期血圧といいます)。動脈内腔が広がることで、血液が全身に送り出されます。血圧が高くなりすぎると、動脈が圧に耐えられず壊れてしまう可能性があります。これを防ぐために、血管を強くする必要があります。
しかし、血管が過度の圧力にさらされると、血管壁が厚く硬くなり、血管の内側が狭くなってしまいます。この状態では、血圧がますます高くなり、さらに悪化する可能性があります。高血圧を放置すると、血管に常に負荷がかかり、この悪循環から脱出できません。
命の危険をともなう重大な病気、合併症
血圧が上がると、血管が硬くなり、内側が狭くなって、細い血管から詰まりやすくなっていきます。細い血管が詰まっても、ほとんど症状は現れません。しかし、腎臓内部の細い血管が少しずつ詰まると、腎機能が少しずつ低下し、いずれ腎不全になります。
また、脳内部の細い血管がつまっていくと、小さな脳梗塞が多発し、いずれ脳血管性認知症になる可能性があります。さらに、動脈硬化が進行して太い血管が詰まると、症状がでやすく、自分で気づきます。
それは脳梗塞であったり、心筋梗塞であったり、命の危険をともなう重大な病気、合併症になります。詰まった細い血管が少ないうちに、太い血管が詰まる前に、高血圧の治療を開始しなければならないのです。
生活習慣の改善について
高血圧を治すためには、まずは薬を使う前に、生活習慣を改善することが大切です。高血圧が軽度の場合、生活習慣を改善するだけで症状が改善することがあります。また、降圧薬を飲んでいる場合でも、生活習慣を改善することで薬の量を減らすことができたり、薬をやめることができる場合があります。
塩分を取りすぎたり、運動不足、肥満が血圧を上げる原因になるので、血圧を下げるためにはこれらの習慣を改善する必要があります。つまり、塩分を控え、運動を取り入れ、健康的な体重を維持することが大切です。
食生活の見直し
 日本人は1日に塩分を10g以上摂取していると言われています。急に減らすことはできませんが、目標は一日6g未満にすることです。
日本人は1日に塩分を10g以上摂取していると言われています。急に減らすことはできませんが、目標は一日6g未満にすることです。
私たちが美味しいと感じるものは塩分が多い食べ物です。味の濃いもの、例えば漬物、味噌汁、ラーメンのスープ、ソースやタレ、ウィンナーやベーコン、ハム、魚の干物などの加工食品は、塩分が多いので注意が必要です。味噌や醤油、ドレッシングで味付けするときは、「かける」よりも「つける」ようにして、塩分が多くならないようにしましょう。
また、お酢などの酸味やだしの旨味を使って味を引き立てましょう。野菜やきのこ、海藻類を十分に摂取し、体から塩分を排出するようにしましょう。肥満も高血圧の原因になることがあります。食べ過ぎや脂肪の多い肉類、お酒や甘いもの、お菓子などの摂りすぎに注意しましょう。1日に必要十分なカロリーを摂取することが大切です。
日常生活に運動をプラスする
 毎日30分ほどの有酸素運動は高血圧の予防や改善に役立ちます。
毎日30分ほどの有酸素運動は高血圧の予防や改善に役立ちます。
水中ウォーキングや軽いジョギングなど、自分に合った運動を選んで始めましょう。忙しくて毎日運動するのが難しい場合は、週に3回、1時間ほどの運動でも効果があります。
運動することで、肥満の解消や予防につながり、血管を拡張して血圧を下げる効果があるため、積極的に取り入れてみましょう。
そのほか、注意したい生活習慣
いびき・睡眠時無呼吸
肥満のある人は、寝ているときに呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群にかかりやすく、その病気が高血圧の原因になることがわかっています。もし睡眠時に呼吸が止まる症状があれば、医師の指示に従って適切な治療を受けることが必要です。
また、睡眠時無呼吸症候群がなくても、寝付きが悪かったり、浅い睡眠だったりすると、血圧が上がりやすくなることがあります。ですから、十分な睡眠時間をとり、睡眠の質を向上させるように心がけましょう。
動脈硬化を進める喫煙習慣
喫煙は、血管を硬くする「動脈硬化」を進めます。この動脈硬化が進むと、血圧が上がってしまいます。もし高血圧になってしまったら、禁煙することが大切です。また、高血圧になる前でも、禁煙をすることで予防することができます。
高血圧症の治療
血圧はどこまで下げるべき?

血圧をどこまで下げるべきかについて、簡単に説明します。
まず、診察室で測定した血圧の場合、高血圧とされる基準値である130/80よりも下げることを目指します。自宅で測定する場合は、目標は125/75未満です。
ただし、年齢が75歳以上で、糖尿病や脳血管障害、慢性腎臓病などの合併症がない場合は、診察室での血圧は140/90未満、自宅での血圧は135/85未満でよいとされています。
薬物療法による改善
生活習慣を改善しても血圧が下がらない場合は、薬を使うことがあります。
降圧薬はたくさんの種類があります。代表的な4種類は、カルシウム拮抗薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、β遮断薬です。患者さんの年齢や病気の状態に合わせて、安全で効果的な薬を選びます。
1種類の薬だけでは十分な降圧効果が得られない場合は、2種類以上の薬を一緒に使うこともあります。
上記4種類の薬剤で、降圧効果が不十分な場合、効果が不十分な場合は第2選択薬が追加されます。第2選択薬には、α遮断薬、中枢性交感神経抑制薬、抗アルドステロン薬などがあり、患者さんの状態に応じて医師が選択します。
怖い話もしましたが、治療を継続的に行うことで、高血圧をコントロールすることができます。生活習慣の改善や薬物療法を行うためには、定期的に内科を受診し、必要な検査を受けることが重要です。
高血圧の症状がないからといって何もしないのではなく、気軽に医療機関に相談しましょう。治療を始めることで、将来の合併症を予防することができます。
高血症のよくあるご質問
高血圧の原因は何ですか?
生活習慣が関与していると考えられています。
高血圧の原因は、一般的には、食生活(例えば、塩分の摂り過ぎや偏った食事)、運動不足、ストレス、肥満などの生活習慣が多く関与していると考えられています。ただし、遺伝的な要因や糖尿病、腎臓疾患、内分泌の異常(副腎ホルモンや甲状腺ホルモンなど)、睡眠時無呼吸など、様々な要因が高血圧の発症に関与することもあります。
高血圧を予防するためにはどのような生活習慣が大切ですか?
まずは食事を見直し、運動する習慣を作りましょう。
高血圧を予防するには、塩分の摂取量を減らし、栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。また、適度な有酸素運動やストレス軽減、禁煙なども効果的です。
高血圧を放置するとどうなりますか?
命を脅かす病気に進展する場合がありますので注意が必要です。
高血圧を放置すると、血管に負荷がかかり、動脈硬化が進行して、心臓病や脳卒中、腎臓疾患など、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。そのため、高血圧は早期発見と治療が非常に重要です。家庭や健康診断で血圧を測定し、早期に発見することが大切です。