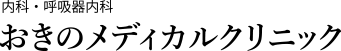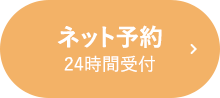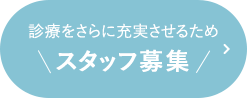動悸・息切れの症状
「動悸・息切れには救心®」というように、動悸と息切れと言えば心臓の病気を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、この二つの症状の原因となる病気は、多種多様です。
動悸および/または息切れを来す疾患として、不整脈、心不全、呼吸不全、肺炎、気胸、喘息、COPD、狭心症、心筋梗塞、肺血栓塞栓症、発熱、脱水、甲状腺機能亢進症、貧血、薬剤、不安神経症、過換気症候群などがあります。
動悸と息切れはどちらも胸で感じることが多く、心臓と肺のどちらから来る症状なのか自分ではよく分からないこともあります。「なんとなく胸が苦しい」「胸がつまるような感じ」といった表現で、動悸や息切れだとは自分では思っていない方もいます。「めまいがする」という訴えで受診して、実は不整脈が原因だったということもあります。
このように様々な病気が考えられる動悸/息切れを自覚したときに、何科に相談すればよいか分からないかもしれません。循環器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患と多岐にわたる可能性があり、いずれにも詳しい医師に受診すると良いでしょう。
動悸や息切れが起こる原因
 子供の頃、体育の授業で激しい運動、例えば50メートル走をした直後のことを思い出してください。心臓の鼓動が速くなり、胸だけではなく耳でもドクンドクンと音を感じます。そして、吸っても吸っても息苦しく、ハーハーゼーゼーと荒くて速い呼吸になります。このように、健康な人でも激しい運動をすれば、動悸・息切れを自覚することができます。
子供の頃、体育の授業で激しい運動、例えば50メートル走をした直後のことを思い出してください。心臓の鼓動が速くなり、胸だけではなく耳でもドクンドクンと音を感じます。そして、吸っても吸っても息苦しく、ハーハーゼーゼーと荒くて速い呼吸になります。このように、健康な人でも激しい運動をすれば、動悸・息切れを自覚することができます。
激しい運動をすると、筋肉をはじめ各臓器が酸素を必要とします。臓器の酸素不足を補うように、無意識のうちに脳が心臓と肺にもっと働くように命令するため、動悸と息切れとして自覚されるのです。しかし、激しい運動とは言えない階段昇降など軽労作で動悸や息切れを感じるのは異常であり、病気の可能性を考えなければなりません。
心臓と肺のどちらか、もしくは両者に異常があると、安静時や軽労作時においても各臓器の酸素需要に応えられず、動悸や息切れとなって現れます。
心臓や肺の機能が正常であっても、甲状腺機能亢進症では組織の代謝が亢進し、組織が酸素不足となるため、動悸・息切れの原因となります。貧血では、血液が酸素を各臓器にうまく運べないため、やはり各臓器が酸素不足となり、動悸・息切れが起こります。
一方、心臓や肺、甲状腺、血液など臓器に全く問題がなくても、脳が勝手に命令することもあります。ストレスや不安障害、パニック障害のように、不安感や焦燥感によって心拍数や呼吸数が発作的に上がってしまいます。
動悸・息切れの検査と治療
まずは問診から
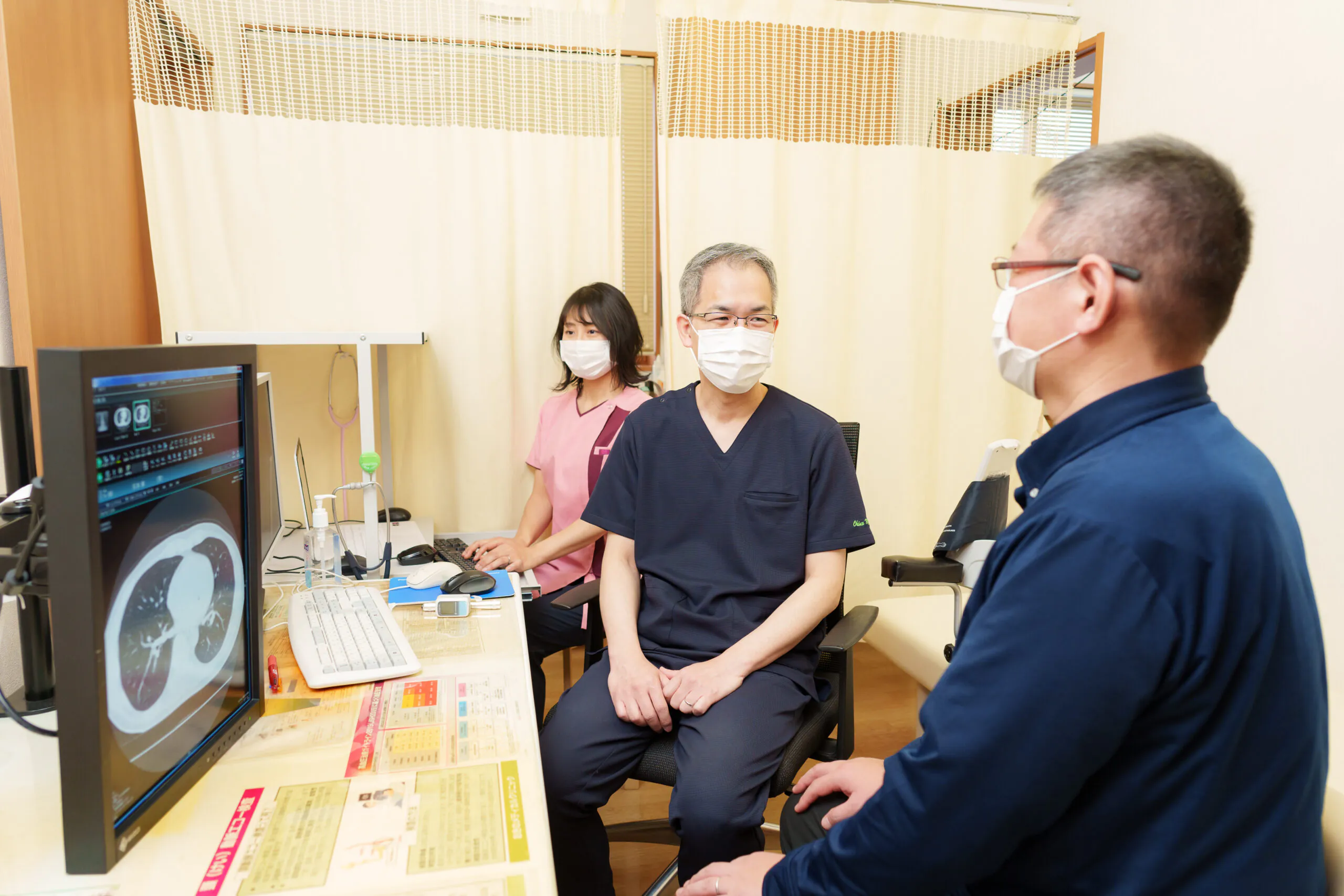 動悸・息切れをきたす疾患は多種多様です。それらをひとつひとつ鑑別していく必要があります。
動悸・息切れをきたす疾患は多種多様です。それらをひとつひとつ鑑別していく必要があります。
受診した際は、まずは問診を行います。
- 動悸と息切れは同時に起こるのか
- どちらか一方のみなのか
- 階段昇降など労作にともなうのか
- 脈は速くなるのか不規則なのか
など、普段の様子を確認します。
次に、内科的診察をします。
- 眼瞼結膜に貧血所見はないか
- 甲状腺腫大はないか
また、
- 心雑音
- 肺雑音
- 心拍数
- 血圧
- 呼吸数
- 不整脈
などを確認します。
そして、必要があれば検査を実施します。
当院で行う検査
 当院では、まず心電図と胸部X線写真をとります。
当院では、まず心電図と胸部X線写真をとります。
心電図
心電図では期外収縮、心房細動、上室性頻拍などを診断します。来院時の心電図で異常がなく、自宅など院外で不整脈が起きていることが疑われる場合、24時間ホルター心電図を実施します。
胸部レントゲン検査
胸部X線写真では心臓の大きさ、肺の陰影の有無を確認し、心不全や肺気腫、気胸、肺炎、間質性肺炎などを鑑別していきます。
肺気腫、COPDなど慢性呼吸器疾患が考えられる場合は、呼吸機能検査や肺CTを追加することもあります。心臓弁膜症や狭心症、心不全などが考えられる場合は、心臓超音波などさらなる精査が必要となりますので、専門医療機関に紹介します。
心臓や肺に問題がない場合、血液検査を行います。赤血球数、ヘモグロビン、甲状腺刺激ホルモン、甲状腺ホルモンを含め一般的な血液検査を行って、貧血や甲状腺機能などに異常がないか調べます。
検査しても異常がない場合
身体的な検査すべてに異常がない場合、ストレスや不安神経症など精神的な問題からくる動悸・息切れを考えます。
動悸・息切れの治し方
代表的な病気の治療法
動悸・息切れの治し方は、原因となる病気によって対処方法が異なります。今回は、代表的な病気の治療法について紹介します。
脈が飛ぶ・胸がつまる
“脈が飛ぶ”“胸がつまる”といった症状の「期外収縮」は、回数がそれほど多くなければ心配の要らない病気ですので、投薬せずに経過観察を行います。症状が強い場合や、頻度が多い場合には、安定剤を飲むと症状が抑えられることがあります。
脈が不規則にうつ
脈が不規則にうつ「心房細動」は心臓内に血栓ができて脳梗塞の原因となります。脳梗塞のリスクを判定して、リスクが高ければ抗凝固療法を行い、血栓を予防します。最近ではカテーテルアブレーションなどの根治的治療が行われることが多くなっており、専門医療機関の不整脈外来に紹介することがあります。
脈が一分間に130回以上が続く
頻脈性不整脈、例えば発作性上室性頻拍や発作性心房細動では緊急対応が必要なことがあります。心電図で頻脈を確認できたら、専門医療機関に救急搬送することがあります。
心機能低下が原因の「心不全」
心機能低下によって心不全が起こると肺に水がたまるため、咳や喘鳴、息切れなど呼吸器症状が前面にでてきます。血中酸素飽和度が低い「呼吸不全」を伴うことが多いため、胸部XpやCT検査で「肺水腫」を確認できたら、入院加療が可能な医療機関で酸素療法や利尿剤、強心剤などで治療を行います。
喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)
「喘息」や「COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患が息切れの原因と考えられる場合、呼気一酸化窒素検査や肺機能検査、CT検査で鑑別診断の上、気管支拡張薬の吸入、抗炎症薬の吸入を行って症状のコントロールを図ります。
そのほか、心臓や肺に問題がない場合
心臓や肺に問題がなく、採血にて貧血や甲状腺機能に異常が確認された場合、さらに原因検索を行います。例えば、鉄欠乏による貧血では鉄剤の内服を行うと、貧血の改善とともに動悸・息切れも改善が期待されます。バセドウ病による甲状腺機能亢進症では、抗甲状腺薬などの治療で動悸も治まってきます。
他にも、ストレスなど心理的な問題で身体に症状が生じる場合は心療内科的なアプローチが必要となることもあります。検査した結果、心臓や肺に問題がないと説明されただけで安心して動悸・息切れが気にならなくなることもあります。
動悸や息切れを感じたら、まずは受診して、医師に解決方法を相談されることをお勧めします。
注意が必要な胸の痛み
 突然の激しい痛みや鈍く続く痛み、呼吸にともなって増減する痛み、胸・背中の痛みなど、多種多様な症状が出ることがあります。
突然の激しい痛みや鈍く続く痛み、呼吸にともなって増減する痛み、胸・背中の痛みなど、多種多様な症状が出ることがあります。
当院へご来院される患者さんも、何か怖い病気ではないかと心配される方が多いです。この場合、まずは命に危険が及ぶ病気を除外することが重要です。
胸痛があらわれる呼吸器の病気は
- 気胸
- 肺炎・気管支炎
- 喘息
- 肺がん
このほか、胸膜炎や気道異物などでも胸痛があらわれることがあります。
中でも、
- 突然の激しい胸の痛み
- 肩や顎の痛み
- 息苦しい
- 血圧が低下している
- 吐き気がある
- 気が遠くなる感じがする(意識レベル低下)
- 顔面蒼白・冷や汗 など
これらの症状が伴う場合は生命に危険が及ぶような重大な病気の可能性があります。
気になる症状があれば、なるべく早めに受診することを心がけ、もしも突然激しい胸痛が起きたら救急車を呼ぶようにしましょう。